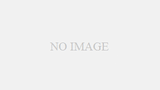「舌がヒリヒリして痛い」「焼けるような感覚が続く」 このような症状でお悩みの方の中には、無意識に歯を接触させる癖が原因となっているケースが多くあります。
歯牙接触癖(しがせっしょくへき)とは、本来なら離れているはずの上下の歯を、無意識に接触させ続ける癖のことです。英語では「Teeth Contact Habit」と呼ばれ、現代人に非常に多く見られる現象です。
この癖が舌痛症の隠れた原因となっていることが、近年の研究で明らかになってきました。多くの方が 「なぜ舌が痛むのかわからない」と悩んでいますが、実は日常の何気ない癖が症状を引き起こしているのです。
今回は歯科口腔外科専門医として、舌痛症と歯牙接触癖の深い関係について詳しく解説いたします。
舌の痛みでお困りの方、無意識に歯を噛みしめている自覚がある方は、ぜひ最後までお読みください。 症状改善への大きなヒントが見つかるはずです。
【歯牙接触癖とは?舌痛症につながる無意識の癖を解説】
歯牙接触癖について正しく理解することは、舌痛症の治療において非常に重要です。まずは、この癖の特徴と舌痛症との関係について詳しく見ていきましょう。
歯牙接触癖の基本的な特徴
正常な歯の状態
健康な状態では、上下の歯は離れているのが正常です。 歯が接触するのは、食事の時の咀嚼(そしゃく)と 飲み込みの瞬間だけで、1日わずか20分程度とされています。
リラックスしている時、会話している時、集中している時など、ほとんどの時間は上下の歯の間に2~3ミリの隙間があります。 この状態を「安静空隙(あんせいくうげき)」と呼びます。
歯牙接触癖の現れ方
歯牙接触癖がある方は、無意識に上下の歯を軽く接触させたり、 強く噛みしめたりしています。本人は気づいていないことがほとんどで、指摘されて初めて自覚することが多いです。
この癖は以下のような場面で現れやすくなります。
- パソコンや携帯電話の操作中
- テレビを見ている時
- 読書や勉強をしている時
- 運転中や電車での移動中
- ストレスを感じている時
歯牙接触癖が舌に与える影響
舌への物理的圧迫
上下の歯が接触すると、その間にある舌は強い圧迫を受けることになります。特に舌の側面部分(舌縁)は、歯に挟まれて持続的な刺激を受けます。
この刺激が慢性的に続くことで、舌の表面に微細な傷ができ、ヒリヒリとした痛みや焼けるような感覚を引き起こします。
舌の血流障害
歯による圧迫が続くと、舌の血流が悪くなります。 血流が悪化すると、舌の組織に十分な酸素や栄養が 行き渡らなくなり、痛みや不快感の原因となります。
舌の位置異常
歯牙接触癖がある方は、舌の位置も異常になりがちです。 舌が常に歯に押し付けられることで、正常な位置からずれてしまい、さらなる刺激を受けやすくなります。
歯牙接触癖の種類と舌痛症への影響度
軽度の接触
上下の歯を軽く接触させる程度の癖です。強い力は かかっていませんが、長時間続くことで舌への 慢性的な刺激となります。
中等度の噛みしめ
歯を軽く噛みしめる状態で、舌への圧迫がより強くなります。 舌の側面に歯型の跡がつくことがあり、舌痛症の症状もより強く現れる傾向があります。
強度の食いしばり
強い力で歯を食いしばる状態です。舌への圧迫が非常に強く、舌痛症だけでなく、顎関節症や歯の破折なども引き起こす可能性があります。
現代社会と歯牙接触癖の増加
デジタル機器の普及
パソコンやスマートフォンの長時間使用により、 歯牙接触癖を持つ方が急激に増加しています。
画面を集中して見ている時、多くの方が無意識に歯を接触させています。これは「デジタル時代の 新しい現代病」とも言えるでしょう。
ストレス社会の影響
現代社会のストレスも歯牙接触癖の大きな原因です。 緊張や不安を感じると、反射的に歯を噛みしめてしまう方が非常に多くいらっしゃいます。
リモートワークの普及により、長時間同じ姿勢で作業する機会が増えたことも、この癖を助長している 要因の一つです。
【舌痛症を引き起こす歯牙接触癖のメカニズムと症状】
歯牙接触癖がどのようなメカニズムで舌痛症を引き起こすのか、 そして具体的にどのような症状が現れるのかを 詳しく解説いたします。
舌痛症発症のメカニズム
段階的な組織変化
歯牙接触癖による舌痛症の発症は、以下のような段階を経て進行します。
第1段階:軽微な圧迫刺激 無意識の歯の接触により、舌に軽い圧迫が加わります。 この段階では症状はほとんど感じられません。
第2段階:慢性刺激の蓄積 同じ刺激が繰り返されることで、舌の組織に微細な炎症が起こり始めます。
第3段階:神経の過敏化 慢性的な炎症により、舌の神経が過敏になり、通常なら痛みを感じない刺激でも痛みとして感じるようになります。
第4段階:舌痛症の発症 神経の過敏化が進行し、持続的な痛みや不快感を感じるようになります。
神経障害性疼痛の発生 長期間の刺激により、舌の神経そのものに障害が起こることがあります。これを「神経障害性疼痛(しんけいしょうがいせいとうつう)」と呼びます。
この状態になると、刺激がなくても痛みを感じたり、軽い刺激でも強い痛みを感じたりするようになります。 舌痛症の中でも特に治療が困難なタイプです。
歯牙接触癖による舌痛症の特徴的症状
痛みの性質 歯牙接触癖が原因の舌痛症では、以下のような 痛みの特徴があります。
- ヒリヒリとした焼けるような痛み
- ピリピリとした電気が走るような感覚
- じんじんとした持続的な痛み
- 舌の表面がざらざらする感じ
症状の出現パターン
- 朝は軽く、夕方にかけて徐々に強くなる
- 集中して作業している時に悪化する
- ストレスを感じた時に症状が強くなる
- 食事中は痛みが和らぐことが多い
痛みの場所 歯牙接触癖による舌痛症では、舌の特定の部位に症状が現れやすい傾向があります。
- 舌の先端部分
- 舌の両側面(舌縁)
- 舌の表面の前方部分
これらの部位は、歯と接触しやすい場所であり、物理的な刺激を受けやすいためです。
併発しやすい症状
口腔乾燥感 歯牙接触癖があると、唾液の分泌量が減少することがあります。 これにより口の中が乾燥し、舌痛症の症状がさらに悪化することがあります。
味覚の変化 舌への慢性的な刺激により、味覚に変化が現れることがあります。 特定の味を感じにくくなったり、口の中に金属のような味を感じたりすることがあります。
睡眠障害 舌の痛みにより、夜間の睡眠が妨げられることがあります。 また、睡眠中の歯ぎしりや食いしばりが、症状をさらに悪化させる悪循環に陥ることもあります。
精神的ストレス 持続する舌の痛みは、大きな精神的ストレスとなります。「なぜ痛むのかわからない」という不安や、「治らないのではないか」という心配が、さらなるストレスを生み出します。
他の病気との鑑別
口腔カンジダ症との違い 口腔カンジダ症では、舌に白い苔のような膜が見られますが、 歯牙接触癖による舌痛症では、見た目の変化はほとんどありません。
舌癌との違い 舌癌では、舌にしこりや潰瘍が現れることが多いですが、 歯牙接触癖による舌痛症では、そのような変化は見られません。ただし、心配な症状がある場合は、必ず専門医の診察を受けることが大切です。
栄養不足による舌炎との違い ビタミンB群不足による舌炎では、舌全体が赤く腫れることがありますが、歯牙接触癖による舌痛症では、局所的な症状が多く見られます。
【歯牙接触癖の改善方法と舌痛症治療のアプローチ】
歯牙接触癖を改善することは、舌痛症の治療において非常に重要です。具体的な改善方法と治療アプローチについて詳しく解説いたします。
歯牙接触癖の自己チェック法
症状の自己観察 まずは、自分に歯牙接触癖があるかどうかを確認することから始めましょう。
チェックポイント:
- 舌の側面に歯型の跡がついている
- 朝起きた時に顎が疲れている感じがする
- 集中している時に歯を接触させている
- ストレスを感じると無意識に歯を噛みしめる
- 頬の内側に白い筋状の跡がある
日常生活での観察 1日の中で、どのような場面で歯を接触させているかを観察してみましょう。
- パソコン作業中
- スマートフォン操作中
- テレビ視聴中
- 読書中
- 運転中
- 考え事をしている時
歯牙接触癖の改善方法
意識的な改善法 歯牙接触癖の改善には、まず自分の癖を意識することが最も重要です。
「唇を閉じて、歯を離す」の実践 正しい口の状態は「唇は軽く閉じて、歯は離れている」 状態です。この状態を意識的に作り、習慣化することが 改善の第一歩です。
リマインダーの活用
- パソコンの画面に付箋を貼る
- スマートフォンのアラーム機能を使用
- 「歯を離す」と書いたメモを目につく場所に貼る
これらのリマインダーにより、定期的に自分の口の状態をチェックする習慣をつけましょう。
ストレス管理 歯牙接触癖の根本的な原因であるストレスを管理することも重要です。
効果的なストレス解消法:
- 深呼吸法やリラクゼーション
- 適度な運動
- 十分な睡眠
- 趣味の時間を作る
- マッサージやストレッチ
専門的な治療法
マウスピース療法 夜間の歯ぎしりや食いしばりがある場合は、 マウスピース(ナイトガード)を使用します。
マウスピースの効果:
- 歯や舌への圧迫を軽減
- 顎関節への負担を減らす
- 歯の摩耗を防ぐ
- 筋肉の緊張を和らげる
咬合調整 歯の噛み合わせに問題がある場合は、咬合調整を行います。 高すぎる詰め物や被せ物を調整することで、 無意識の歯の接触を減らすことができます。
筋弛緩療法 顎や首の筋肉の緊張を和らげる治療法です。
- 理学療法によるマッサージ
- 温熱療法
- 超音波療法
- 筋弛緩薬の使用
舌痛症に対する直接的な治療
薬物療法 歯牙接触癖の改善と並行して、舌の痛みに対する 薬物療法も行います。
使用される薬剤:
- 神経障害性疼痛治療薬
- 三環系抗うつ薬(低用量使用)
- 局所麻酔薬
- 保湿剤や人工唾液
レーザー治療 低出力レーザーによる治療により、舌の炎症を抑制し、組織の修復を促進することができます。
口腔ケアの改善
- 優しい歯磨き
- アルコールフリーの洗口液使用
- 舌ブラシでの適切な舌清掃
- 口腔保湿剤の使用
生活習慣の改善
作業環境の見直し 長時間のデスクワークが歯牙接触癖の原因となっている場合は、作業環境を見直しましょう。
- 適切な椅子と机の高さ
- モニターの位置調整
- 定期的な休憩の取り方
- 正しい姿勢の維持
食生活の改善 舌への刺激を減らすために、食事内容も見直しましょう。
避けるべき食品:
- 辛い食べ物
- 酸味の強い食品
- 熱すぎる飲み物
- アルコール
推奨される食品:
- 柔らかい食べ物
- 栄養バランスの良い食事
- ビタミンB群を含む食品
- 十分な水分摂取
治療の効果と経過
改善の目安 歯牙接触癖の改善による舌痛症の治療効果は、 個人差がありますが、多くの場合で改善が期待できます。
- 軽度の場合:2~4週間で改善
- 中等度の場合:1~3ヶ月で改善
- 重度の場合:3~6ヶ月以上かかることもある
治療継続の重要性 歯牙接触癖は長年の習慣であるため、改善には時間がかかります。症状が軽くなっても、治療を継続することが再発防止につながります。
定期的な歯科検診を受け、専門医と連携しながら 治療を進めることが成功の鍵となります。
まとめ
舌痛症と歯牙接触癖には密接な関係があり、無意識の歯の接触が舌の慢性的な痛みを引き起こすことが 明らかになっています。
現代社会では、デジタル機器の長時間使用やストレスの増加により、歯牙接触癖を持つ方が急激に増えています。 この癖が舌痛症の隠れた原因となっているケースが非常に多いのです。
治療には、まず自分の癖を自覚し、意識的に改善していくことが最も重要です。「唇を閉じて、歯を離す」という 正しい口の状態を習慣化することから始めましょう。
同時に、ストレス管理や生活習慣の改善も欠かせません。 専門医による適切な診断と治療を受けながら、 根気よく改善に取り組むことが大切です。
舌の痛みでお悩みの方は、歯牙接触癖の可能性も考慮して、 歯科口腔外科を受診することをお勧めします。 適切な治療により、快適な日常生活を取り戻すことが可能です。