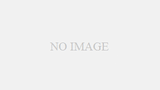「顎が痛い」「口が開かない」「顎からカクカク音がする」 このような症状でお悩みの方の多くに、無意識に歯を 接触させる癖があることをご存知でしょうか。
顎関節症(がくかんせつしょう)は、顎の関節や筋肉に 問題が生じる病気です。一方、歯牙接触癖(しがせっしょくへき)は 本来離れているはずの上下の歯を、無意識に接触させ続ける 癖のことです。
近年の研究により、この二つには密接な関係があることが 明らかになってきました。多くの顎関節症患者さんに 歯牙接触癖が見られ、この癖が症状を悪化させる 重要な要因となっています。
現代社会では、デジタル機器の普及やストレスの増加により、 歯牙接触癖を持つ方が急激に増えています。それに伴って 顎関節症で悩む方も増加傾向にあります。
今回は歯科口腔外科専門医として、顎関節症と歯牙接触癖の 関係について詳しく解説いたします。顎の症状でお困りの方、 無意識に歯を噛みしめている自覚がある方は、 ぜひ最後までお読みください。
【顎関節症と歯牙接触癖の基本的な関係を専門医が解説】
顎関節症と歯牙接触癖の関係を理解するために、 まずはそれぞれの特徴と相互作用について 詳しく見ていきましょう。
顎関節症の基本的な特徴
顎関節症とは 顎関節症は、顎の関節(顎関節)や、顎を動かす筋肉 (咀嚼筋)に問題が生じる病気の総称です。 正式には「顎関節・咀嚼筋障害」と呼ばれています。
主な症状には以下があります。
- 顎の痛み
- 口が開かない(開口障害)
- 顎を動かすときの雑音
- 噛み合わせの違和感
- 頭痛や肩こり
顎関節症の分類 顎関節症は原因や症状によって、以下のように分類されます。
I型:咀嚼筋の異常 顎を動かす筋肉の緊張や炎症が主な原因です。 歯牙接触癖が最も関係しやすいタイプです。
II型:関節包や靭帯の異常 顎関節を包む膜や靭帯に問題が生じるタイプです。
III型:関節円板の異常 顎関節の中にあるクッションの役割をする軟骨 (関節円板)がずれるタイプです。
IV型:骨の異常 顎関節の骨そのものに変形や炎症が生じるタイプです。
歯牙接触癖の特徴と現れ方
正常な歯の状態 健康な状態では、上下の歯は離れているのが正常です。 歯が接触するのは、食事での咀嚼と飲み込みの瞬間だけで、 1日わずか20分程度とされています。
安静時には上下の歯の間に2~3ミリの隙間があり、 これを「安静空隙(あんせいくうげき)」と呼びます。
歯牙接触癖の現れ方 歯牙接触癖がある方は、以下のような場面で 無意識に歯を接触させています。
- パソコンやスマートフォンの操作中
- テレビ視聴や読書中
- 集中して作業している時
- ストレスを感じている時
- 運転中や電車での移動中
本人は気づいていないことがほとんどで、 指摘されて初めて自覚することが多いです。
歯牙接触癖が顎関節症に与える影響
咀嚼筋への持続的な負担 上下の歯が接触している間、顎を動かす筋肉 (咀嚼筋)は常に緊張状態にあります。
通常なら休んでいるはずの筋肉が、長時間にわたって 働き続けることで、筋肉疲労や炎症を起こします。 これが顎関節症の直接的な原因となります。
顎関節への圧迫 歯の接触により、顎関節にも持続的な圧迫力が加わります。 この圧迫が関節の炎症や変形を引き起こし、 顎関節症の症状を悪化させます。
関節円板の位置異常 持続的な筋肉の緊張により、関節円板の位置がずれやすく なります。これにより、顎を動かすときの「カクカク音」や 「ガリガリ音」が生じることがあります。
悪循環のメカニズム
症状の相互悪化 顎関節症と歯牙接触癖は、お互いを悪化させる 悪循環を形成します。
- 歯牙接触癖により筋肉が緊張
- 筋肉の緊張が顎関節症の症状を引き起こす
- 痛みやストレスにより、さらに歯を接触させる
- 症状がさらに悪化する
この悪循環を断ち切ることが、治療成功の鍵となります。
ストレスとの関係 現代社会のストレスは、歯牙接触癖と顎関節症の 両方を悪化させる重要な要因です。
ストレスを感じると、反射的に歯を噛みしめる方が多く、 これが症状をさらに悪化させます。また、顎の痛みや 不快感がストレスとなり、さらなる悪循環を生み出します。
現代社会での増加要因
デジタル機器の普及 パソコンやスマートフォンの長時間使用により、 歯牙接触癖を持つ方が急激に増加しています。
画面を集中して見ている時、多くの方が無意識に 歯を接触させており、これが顎関節症の増加要因と なっています。
リモートワークの影響 新型コロナウイルスの影響でリモートワークが普及し、 長時間同じ姿勢でパソコン作業をする機会が増えました。
これにより歯牙接触癖が増加し、顎関節症で悩む方も 急激に増えています。
生活習慣の変化 現代人の生活習慣の変化も、顎関節症増加の要因です。
- 柔らかい食べ物中心の食生活
- 運動不足
- 睡眠不足
- ストレスの増加
これらの要因が複合的に作用し、顎関節症の 発症リスクを高めています。
【顎関節症の症状と歯牙接触癖による影響の現れ方】
歯牙接触癖が顎関節症に与える具体的な影響と、 それによって現れる症状について詳しく解説いたします。
歯牙接触癖による顎関節症の特徴的症状
顎の痛み 歯牙接触癖による顎関節症では、特徴的な痛みのパターンが 見られます。
痛みの特徴:
- 朝起きた時に顎が重く感じる
- 長時間の作業後に痛みが強くなる
- 集中している時に顎に違和感を感じる
- ストレスを感じた後に痛みが悪化する
痛みの場所:
- 耳の前あたり(顎関節部)
- 頬の筋肉
- こめかみ付近
- 顎の下の筋肉
開口障害(口が開かない) 筋肉の緊張により、口を大きく開けることが 困難になります。
正常な開口量:指3本分(約4センチ) 開口障害:指2本分以下(約3センチ以下)
開口障害の現れ方:
- 朝起きた時に口が開きにくい
- 大きなものを食べる時に困る
- あくびをする時に痛みを感じる
- 歯科治療で口を開けるのがつらい
顎関節雑音 歯牙接触癖により関節円板の位置が変化すると、 顎を動かす時に音が生じます。
音の種類:
- カクカク音:関節円板のずれによる音
- ガリガリ音:関節面の摩擦による音
- ポキポキ音:関節包内の圧力変化による音
音が出るタイミング:
- 口を開ける時
- 食べ物を噛む時
- 話をしている時
- あくびをする時
全身への影響と症状
頭痛 顎の筋肉の緊張は、頭部の筋肉にも影響を与え、 頭痛を引き起こします。
頭痛の特徴:
- こめかみ付近の痛み
- 後頭部の重い感じ
- 目の奥の痛み
- 朝起きた時の頭痛
肩こり・首こり 顎の筋肉と首や肩の筋肉は連動しているため、 顎関節症により肩こりや首こりが生じます。
症状の現れ方:
- 肩の重い感じ
- 首の後ろの張り
- 肩甲骨周辺の痛み
- 腕のしびれ(重症の場合)
睡眠障害 顎の痛みや不快感により、睡眠の質が低下します。 また、睡眠中の歯ぎしりや食いしばりが、 症状をさらに悪化させることがあります。
睡眠への影響:
- 寝つきが悪い
- 夜中に目が覚める
- 朝起きても疲れが取れない
- 歯ぎしりで家族に迷惑をかける
食事への影響
咀嚼困難 顎の痛みや開口障害により、食事に支障をきたします。
困る場面:
- 硬いものが噛めない
- 大きな食べ物が食べられない
- 長時間の咀嚼で疲れる
- 食事の途中で顎が痛くなる
栄養バランスの悪化 食べられるものが限られることで、栄養バランスが 悪化することがあります。
影響:
- 柔らかいものばかり食べる
- 野菜や肉類の摂取不足
- 栄養不足による体調不良
- 体重減少(重症の場合)
精神的な影響
不安やストレス 慢性的な顎の症状は、大きな精神的ストレスとなります。
心理的影響:
- 症状への不安
- 治るかどうかの心配
- 日常生活への支障からくるイライラ
- 社会生活への影響による孤立感
うつ症状 長期間の症状により、うつ症状が現れることがあります。
症状:
- 気分の落ち込み
- 意欲の低下
- 集中力の低下
- 食欲不振
症状の日内変動
朝の症状 睡眠中の歯ぎしりや食いしばりにより、 朝起きた時に症状が強く現れることが多いです。
朝の特徴的症状:
- 顎の重い感じ
- 口が開きにくい
- 頭痛
- 肩こり
夕方の症状悪化 1日の疲労やストレスの蓄積により、 夕方から夜にかけて症状が悪化します。
夕方以降の症状:
- 顎の痛みの増強
- 筋肉の張り感
- 疲労感
- イライラ感
他の病気との鑑別
三叉神経痛との違い 三叉神経痛は、顔面に走る鋭い痛みが特徴ですが、 顎関節症は筋肉の痛みが中心となります。
耳の病気との違い 顎関節は耳の近くにあるため、耳の痛みと 間違われることがありますが、聴力に問題はありません。
歯の病気との違い 顎関節症による痛みは、特定の歯ではなく、 顎全体や筋肉に現れます。
【歯牙接触癖の改善による顎関節症治療と予防法】
歯牙接触癖を改善することは、顎関節症の治療において 最も重要なアプローチの一つです。具体的な改善方法と 治療法について詳しく解説いたします。
歯牙接触癖の自己チェックと気づき
セルフチェック法 まずは自分に歯牙接触癖があるかどうかを 確認しましょう。
チェックポイント:
- 舌の側面に歯型の跡がついている
- 頬の内側に白い筋状の跡がある
- 朝起きた時に顎が疲れている
- 集中している時に歯を接触させている
- ストレス時に無意識に歯を噛みしめる
日常での観察 どのような場面で歯を接触させているかを 観察してみましょう。
よくある場面:
- パソコン作業中
- スマートフォン操作中
- テレビ視聴中
- 読書や勉強中
- 運転中
- 考え事をしている時
歯牙接触癖の基本的な改善方法
「唇を閉じて、歯を離す」の実践 正しい口の状態は「唇は軽く閉じて、歯は離れている」 状態です。この状態を意識的に作り、習慣化することが 改善の第一歩です。
実践方法:
- 現在の口の状態を確認する
- 歯が接触していたら、意識的に離す
- 唇は軽く閉じたまま保つ
- 舌は下顎の歯の裏側に軽く触れる程度
リマインダーの活用 意識的に口の状態をチェックする習慣をつけるために、 リマインダーを活用しましょう。
効果的な方法:
- パソコンの画面に「歯を離す」と書いた付箋を貼る
- スマートフォンのアラーム機能を1時間おきに設定
- 目につく場所にメモを貼る
- 腕時計のアラーム機能を活用
深呼吸とリラクゼーション ストレスによる歯牙接触癖を改善するために、 リラクゼーション法を取り入れましょう。
深呼吸法:
- ゆっくりと4秒間息を吸う
- 4秒間息を止める
- 8秒間かけてゆっくり息を吐く
- これを3~5回繰り返す
専門的な治療法
マウスピース療法 夜間の歯ぎしりや食いしばりを防ぐために、 マウスピース(ナイトガード)を使用します。
マウスピースの効果:
- 歯や顎関節への負担軽減
- 筋肉の緊張緩和
- 歯の摩耗防止
- 関節円板の保護
マウスピースの種類:
- ハードタイプ:耐久性が高く、調整しやすい
- ソフトタイプ:装着感が良いが、耐久性に劣る
- 部分タイプ:前歯部分のみの小さなタイプ
理学療法 筋肉の緊張を和らげ、関節の動きを改善するために 理学療法を行います。
温熱療法:
- ホットパック
- 温湿布
- 入浴時の温浴
マッサージ療法:
- 咀嚼筋のマッサージ
- 首や肩のマッサージ
- セルフマッサージの指導
運動療法:
- 顎の開閉運動
- 首や肩のストレッチ
- 全身の軽い運動
薬物療法 症状に応じて、薬物療法も併用します。
使用される薬剤:
- 消炎鎮痛薬:痛みや炎症を抑える
- 筋弛緩薬:筋肉の緊張を和らげる
- 抗不安薬:ストレスや不安を軽減
- 睡眠導入薬:睡眠の質を改善
生活習慣の改善
作業環境の見直し 長時間のデスクワークが歯牙接触癖の原因となっている 場合は、作業環境を改善しましょう。
改善ポイント:
- 椅子と机の適切な高さ調整
- モニターの位置と角度の最適化
- 1時間ごとの休憩と体操
- 正しい姿勢の維持
ストレス管理 ストレスは歯牙接触癖と顎関節症の重要な悪化要因です。 効果的なストレス管理法を身につけましょう。
ストレス解消法:
- 適度な運動(ウォーキング、ヨガなど)
- 趣味の時間を作る
- 友人や家族との時間を大切にする
- 十分な睡眠を取る
- バランスの良い食事を心がける
食生活の改善 顎関節症の症状がある間は、顎に負担をかけない 食事を心がけましょう。
推奨される食事:
- 柔らかく調理した食品
- 小さく切った食べ物
- 栄養バランスの良い食事
- 十分な水分摂取
避けるべき食品:
- 硬い食べ物(せんべい、ナッツなど)
- 大きな食べ物(ハンバーガーなど)
- ガムや硬いキャンディー
- 氷をかむ習慣
治療の効果と予後
改善の目安 歯牙接触癖の改善による顎関節症の治療効果は、 症状の程度や個人差により異なります。
軽度の場合:2~4週間で改善 中等度の場合:1~3ヶ月で改善 重度の場合:3~6ヶ月以上かかることもある
継続的なケアの重要性 歯牙接触癖は長年の習慣であるため、改善には 継続的な取り組みが必要です。
症状が改善しても、定期的な歯科検診を受け、 専門医と連携しながら再発防止に努めることが 大切です。
予防のポイント
- 正しい口の状態の維持
- ストレス管理の継続
- 定期的な歯科検診
- 生活習慣の改善
- 早期発見・早期治療
まとめ
顎関節症と歯牙接触癖には密接な関係があり、 無意識の歯の接触が顎の痛みや機能障害を 引き起こす重要な原因となっています。
現代社会では、デジタル機器の普及やストレスの増加により、 歯牙接触癖を持つ方が急激に増えており、それに伴って 顎関節症で悩む方も増加しています。
治療の基本は、歯牙接触癖の改善です。「唇を閉じて、 歯を離す」という正しい口の状態を意識し、習慣化する ことから始めましょう。同時に、ストレス管理や 生活習慣の改善も重要です。
専門的な治療として、マウスピース療法、理学療法、 薬物療法などがあります。症状に応じて、これらの 治療法を組み合わせて行います。
顎の症状でお悩みの方は、早めに歯科口腔外科を受診し、 適切な診断と治療を受けることをお勧めします。 歯牙接触癖の改善により、多くの場合で症状の改善が 期待できます。
一人で悩まず、専門医と連携しながら治療に取り組み、 快適な日常生活を取り戻しましょう。